先日こんな相談をいただきました。※プライバシー保護の関係で、内容の一部を変更しております。
4月から中学生になった息子は部屋が汚いしぐちゃぐちゃです。お菓子のゴミを隙間に溜めてそのままです。
どうすればいいでしょうか。
子どもの部屋が荒れていると、「もう中学生なのに片付けもできないの?」と思ってしまいますよね。
しかし、少し対応を工夫すれば改善することができます。そこで今回は、「片付けられない子どもの改善法」についてお伝えしましょう。
片付けられない理由と効果的な対策を知ることで、子どもが自ら片付けるようになります。親の負担やストレスは減り、子どもの自立にもつながります。
片付けられない3つの理由

子どもが片付けられない理由は、主に3つあります。まずはどの理由に当てはまるか、確認してみましょう。
1つ目は「親子関係が悪い」からです。愛情バロメータが低いと、子どもの気力が低下します。すると「片付けをやろう」という気持ちが出なくなるでしょう。
2つ目は「やり方を知らない」ことです。何をどこに片付ければいいかわからないと、片付けたくても片付けられません。
3つ目は「発達障害」の可能性です。発達障害の特性によって、計画を立てたり、優先順位をつけたり、行動を始めたりする力が弱いことがあります。
そのため、どこから手をつけていいかわからず、片付けが進まないことがあります。
片付け習慣を身につける3ステップ

基本的には3ステップで、子どもの片付け習慣を育てることができます。
ステップ1は「愛情バロメータを上げること」、ステップ2は「一緒にやりながら教えること」です。
愛情バロメータを上げるために、日ごろから子どもの正常な要求をできる限り聞きましょう。
また、いきなり「片付けなさい」と言ってもやり方がわからなければできません。最初は「一緒にやろうか」と声をかけて、並走するつもりで教えましょう。
ステップ3は「具体的なルールを決めること」です。子どもと話し合いながら、
- 物の定位置(服はここにかける、ゴミはここに捨てる、プリントはここに入れるなど)
- 片付けるタイミング(毎日寝る前に片付ける、週に1回片付けるなど)
- 親が声をかけるタイミング(約束の日に片付けていなかったらいつ声をかけるか)
発達障害の可能性がある場合の対応

発達障害の可能性がある場合も、まずは上記のステップを行ってみてください。それでもうまくいかない場合は、次の点を意識しましょう。
1つ目は「基準を下げること」です。年齢相応の基準ではなく、能力に合わせた基準で接しましょう。
たとえば、プリントを種類ごとにわけることが難しければ、「わからないプリントは全部ここに入れておく」といったシンプルなルールがおすすめです。
2つ目は「すぐにできなくても叱らないこと」です。できていないことを叱るより、少しでもうまくいったことを褒めるようにしましょう。
3つ目は「専門家と連携すること」です。発達障害の診断がある場合は、公認心理師など専門家のサポートを受けることも考えましょう。
専門的なアドバイスをもとに進めることで、習慣化しやすくなります。
本日のまとめ

片付けられない子どもには、「親子関係改善」「やり方を教える」「具体的なルール設定」という3ステップで対応しましょう。
発達障害の可能性がある場合は、基準を下げて専門家と連携することを考えてみるのがおすすめです。
大切なのは、子どもの状況を理解し、適切なサポートをすることです。イライラして叱るのではなく、一緒に解決する姿勢を意識しましょう。
明日ですが、「高校受験やる気UP勉強会2025を行いました」というお話をします。本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。
思春期の子育てアドバイザー道山ケイ


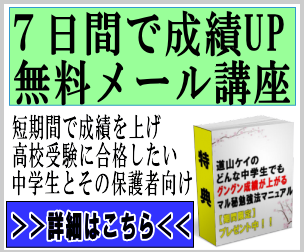
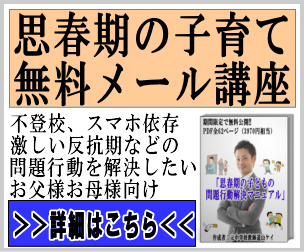












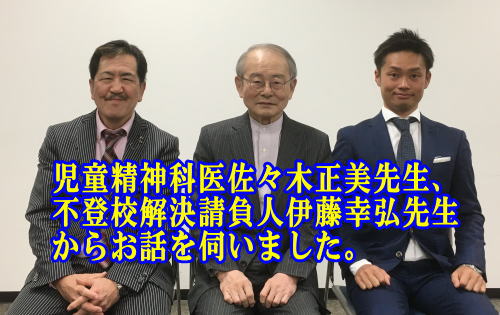
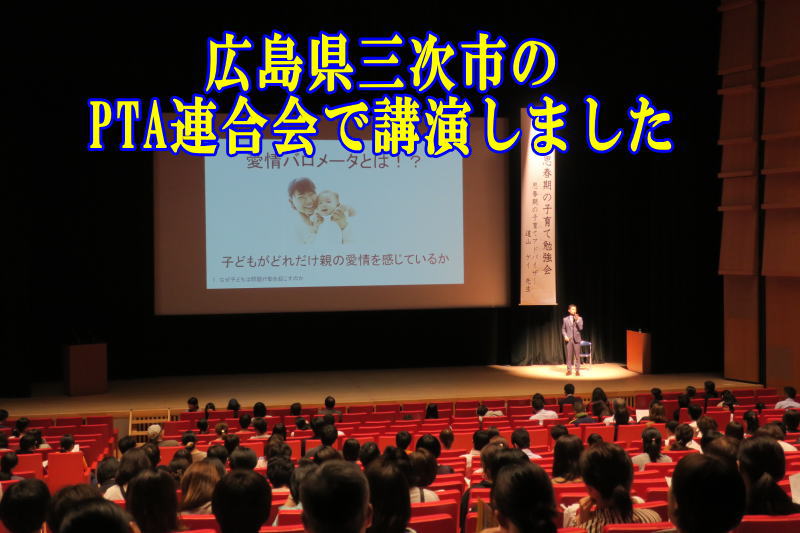

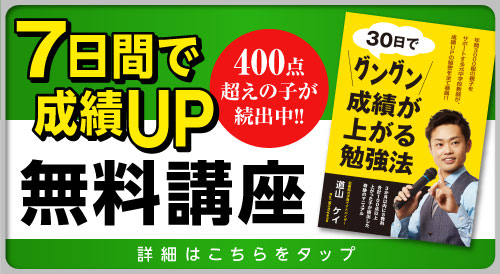
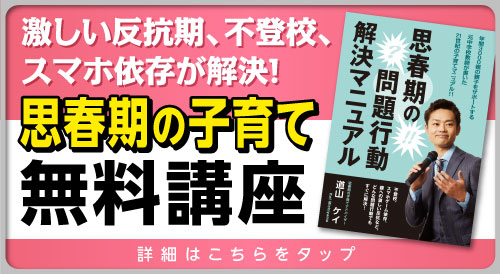













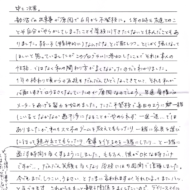






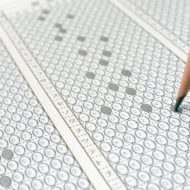






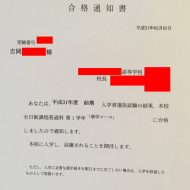

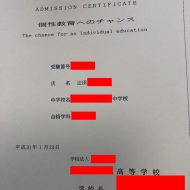


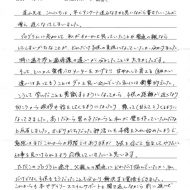




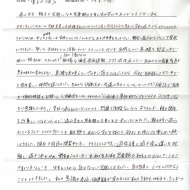


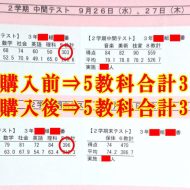

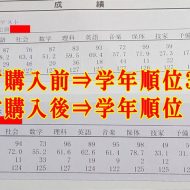
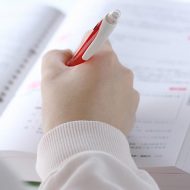
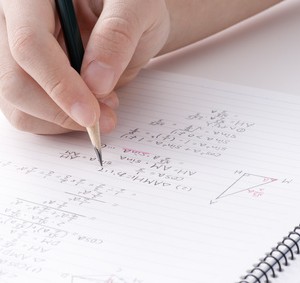


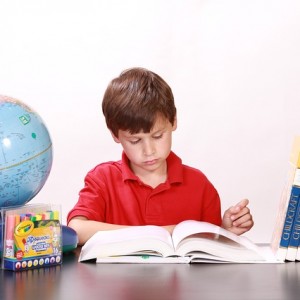
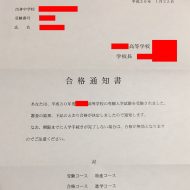




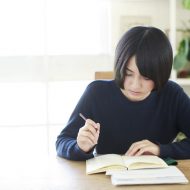
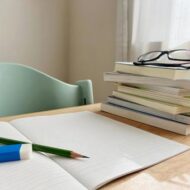



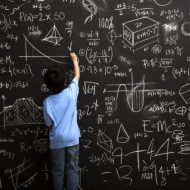

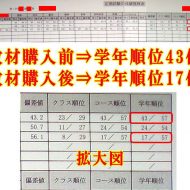


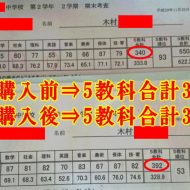
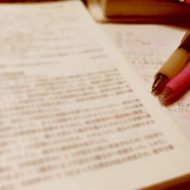
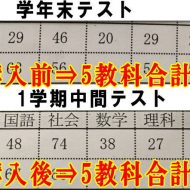

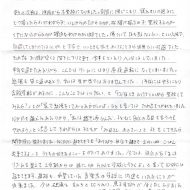

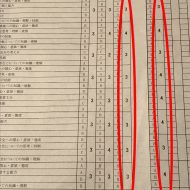



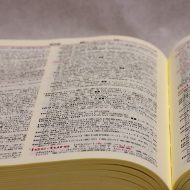

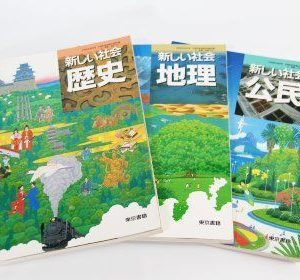
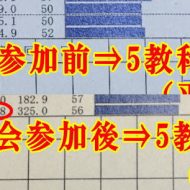

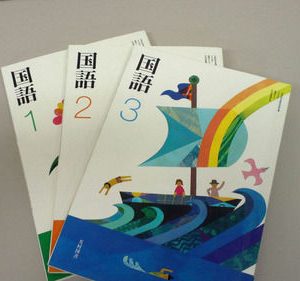


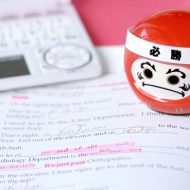



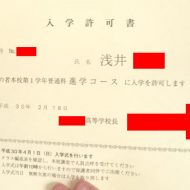
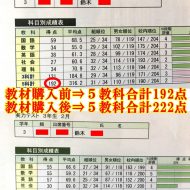

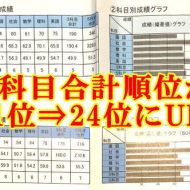
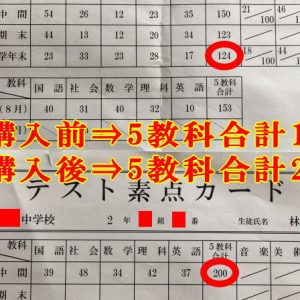











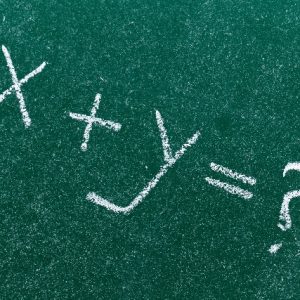





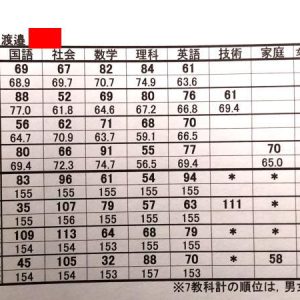
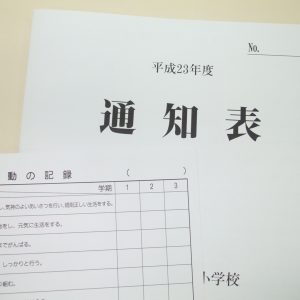
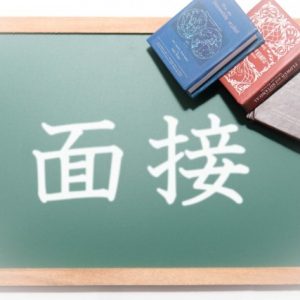
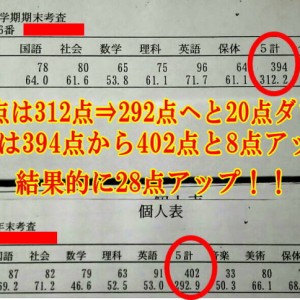



この記事へのコメントはありません。